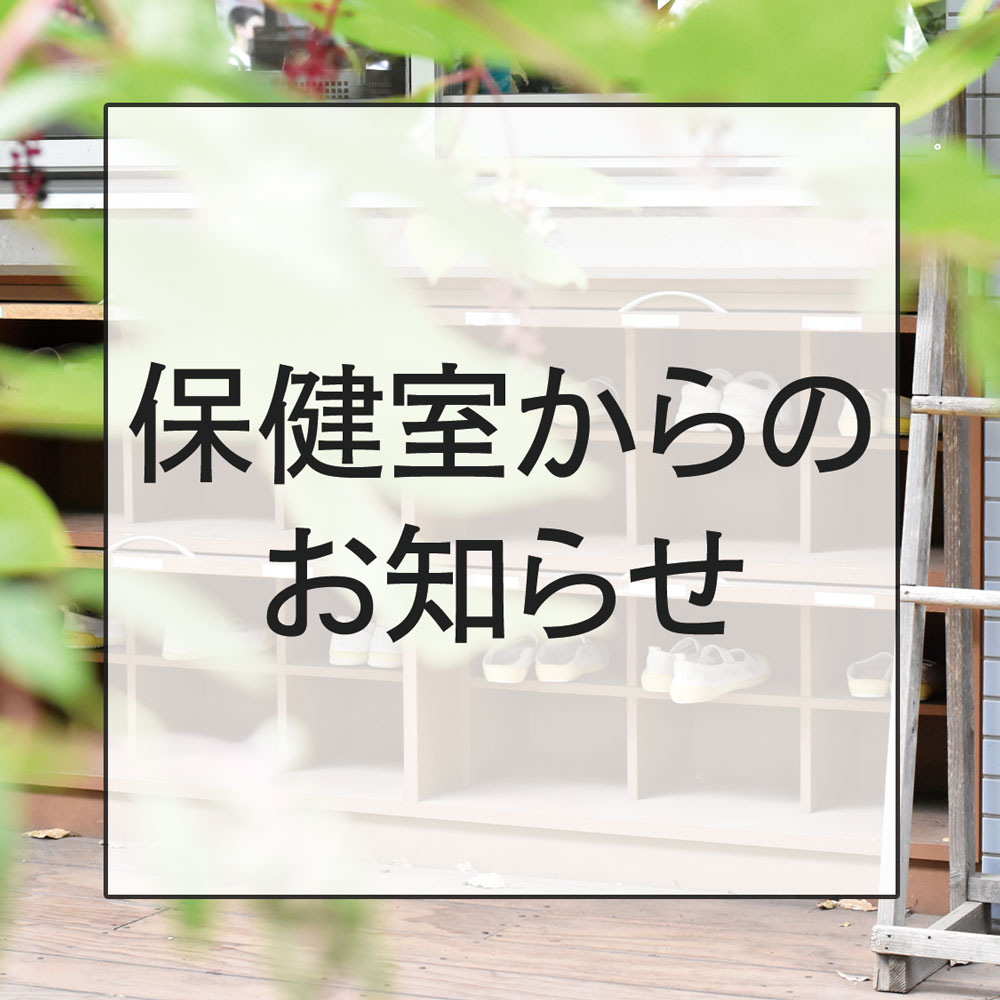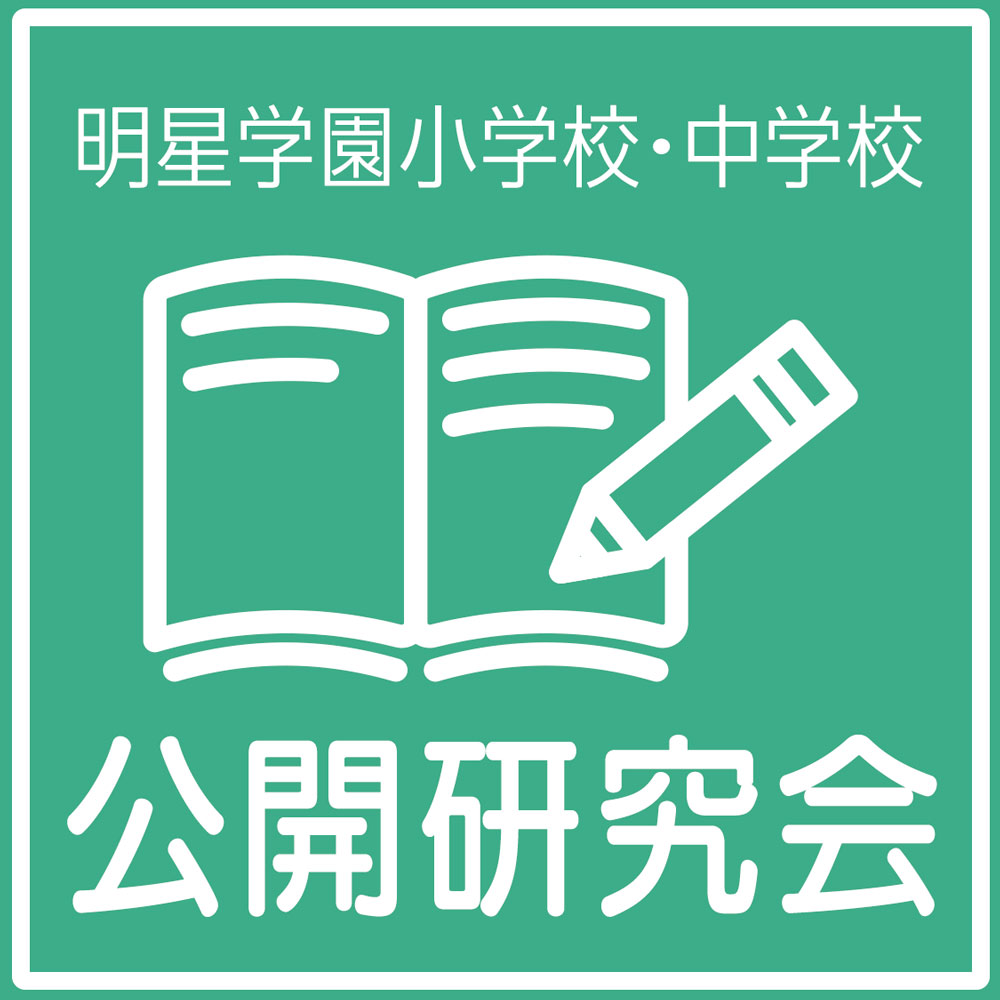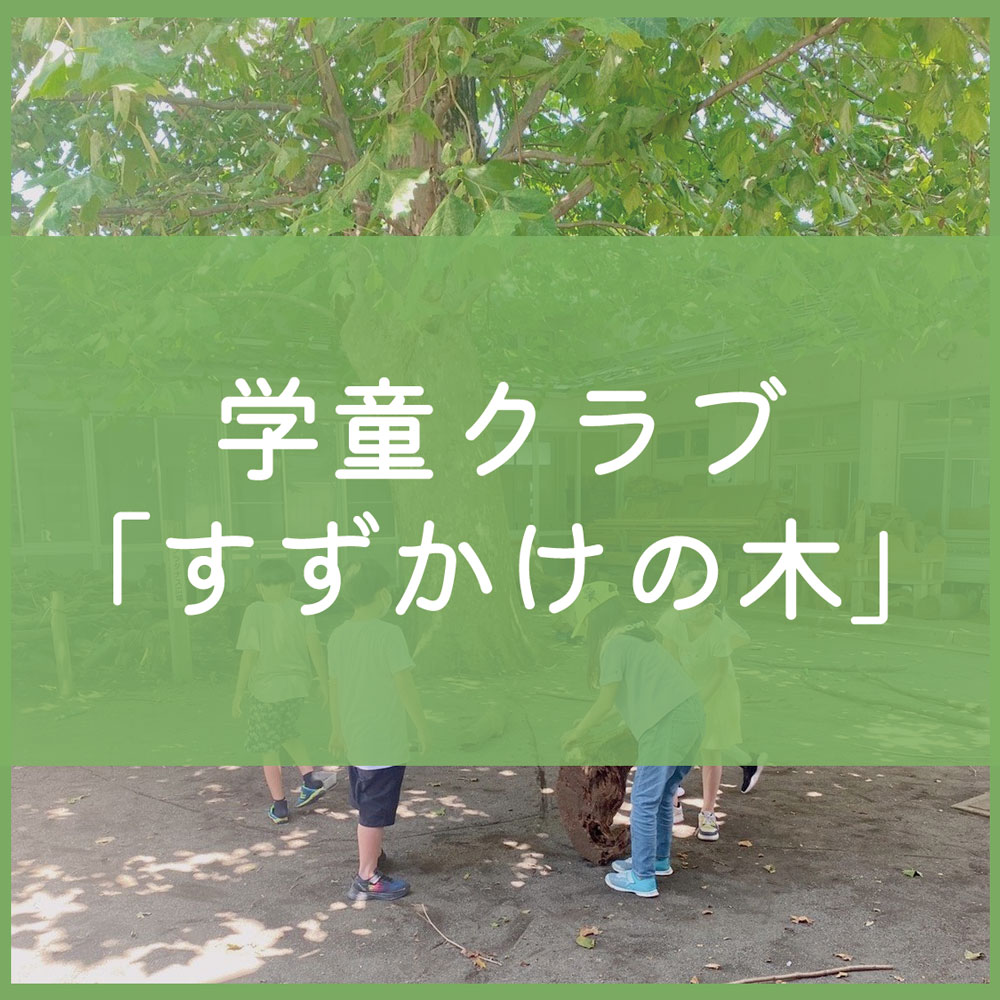小学校
先生コラム
5年社会科☆矢じりづくり!
縄文時代体験の第3弾!
本日は、5年合同「矢じり作り」体験でした。
土器作り、弓矢体験と重ね、今回はもっとも危ない体験です。
作業を始める前に、縄文時代からのスペシャルゲスト、えぐっちゃん(社会科専科教員)から説明と実演をしてもらいました。
- 事前のお話を真剣に聞いている子どもたち!
矢じりは弓矢の矢の先につける道具です。
この弓矢の発明により、獲物を遠くからでも仕留め、安全にかつ確実に得ることができるようになりました。
弓矢のおかげで人々の生活が豊かになったのです。また、殺傷能力を高めるために、矢じりは作られました。
その素材でもっとも使われたのが、黒曜石です。
黒曜石はガラス質で、その剥片はするどく、切れ味が抜群です。そのため黒曜石を求めて交易が行われていたことを授業でも学習しました。
いざ、矢じり作りに挑戦です。
現代人である私たちは、手には皮手袋をはめ、ひざ(もも)にはなめした皮を置き、目には防護メガネをかけ、けがをしないように万全に取り組みました。
黒曜石のどこをたたいたら割れるのか、どうしたら形のいい破片がとれるのか、初めは試行錯誤していましたが、時間が経つにつれてコツをつかみ、ちょうどいい剝片が取れるようになりました。
用意していた鶏肉を切ると、皮まで簡単に切ることができました。何度も何度もたたき割り、たくさんの剥片をゲットし、加工して矢じりを作ることができました。
縄文人の道具を作る喜びと苦労を味わうことができ、体験後のレポートには作り方やコツ、感想と学んだことをまとめることができました。
(担任 社会科担当 藤條)