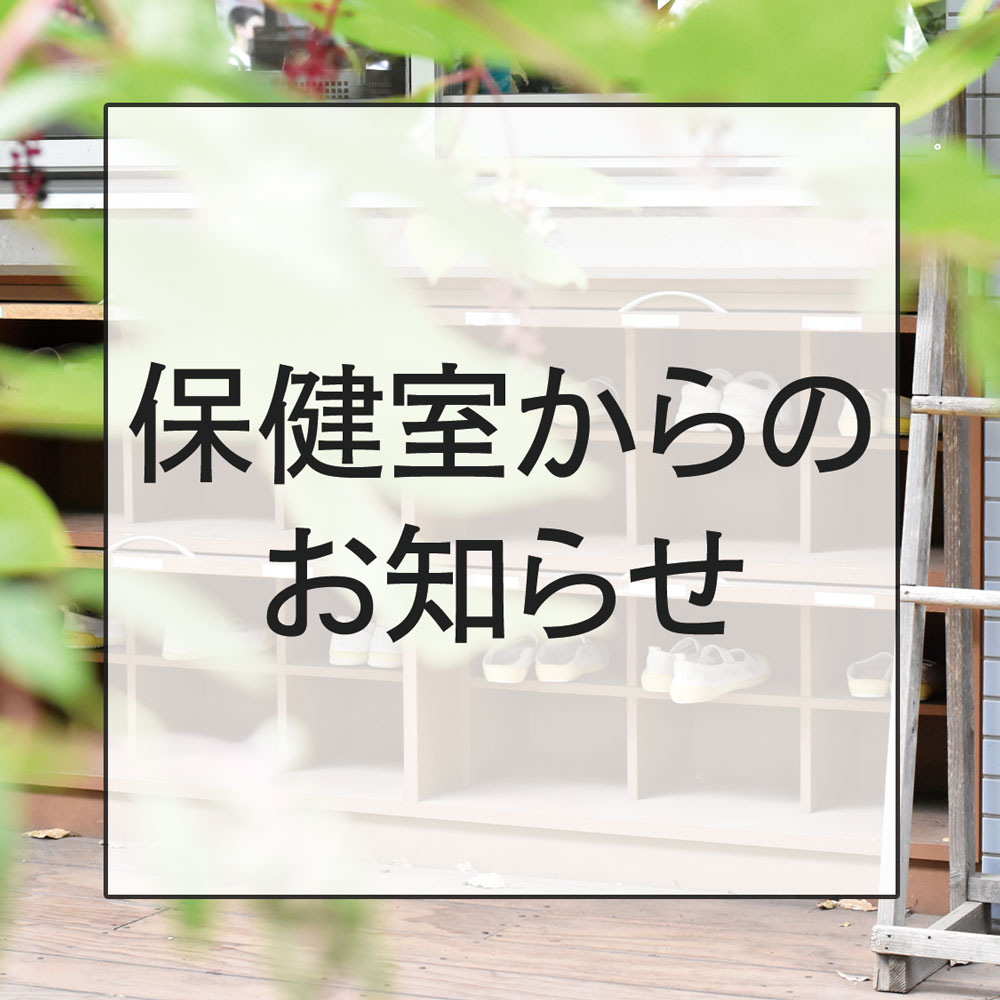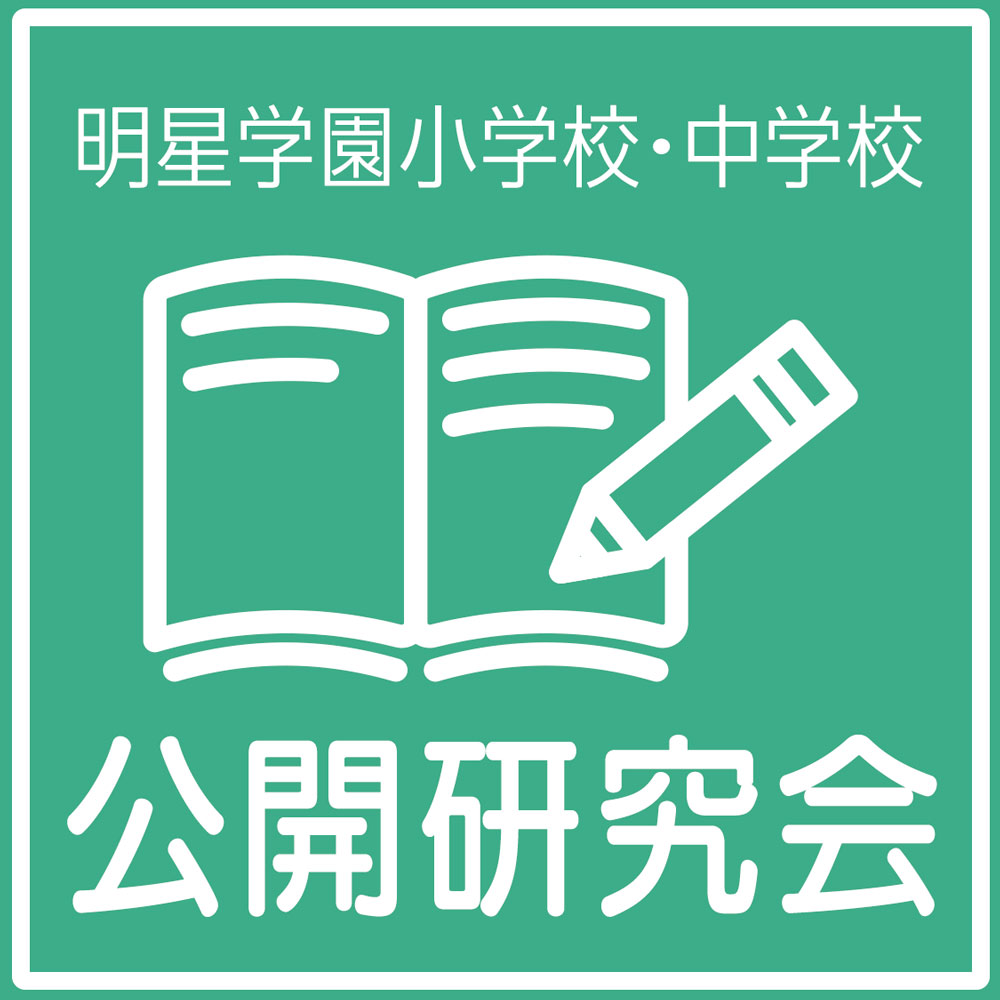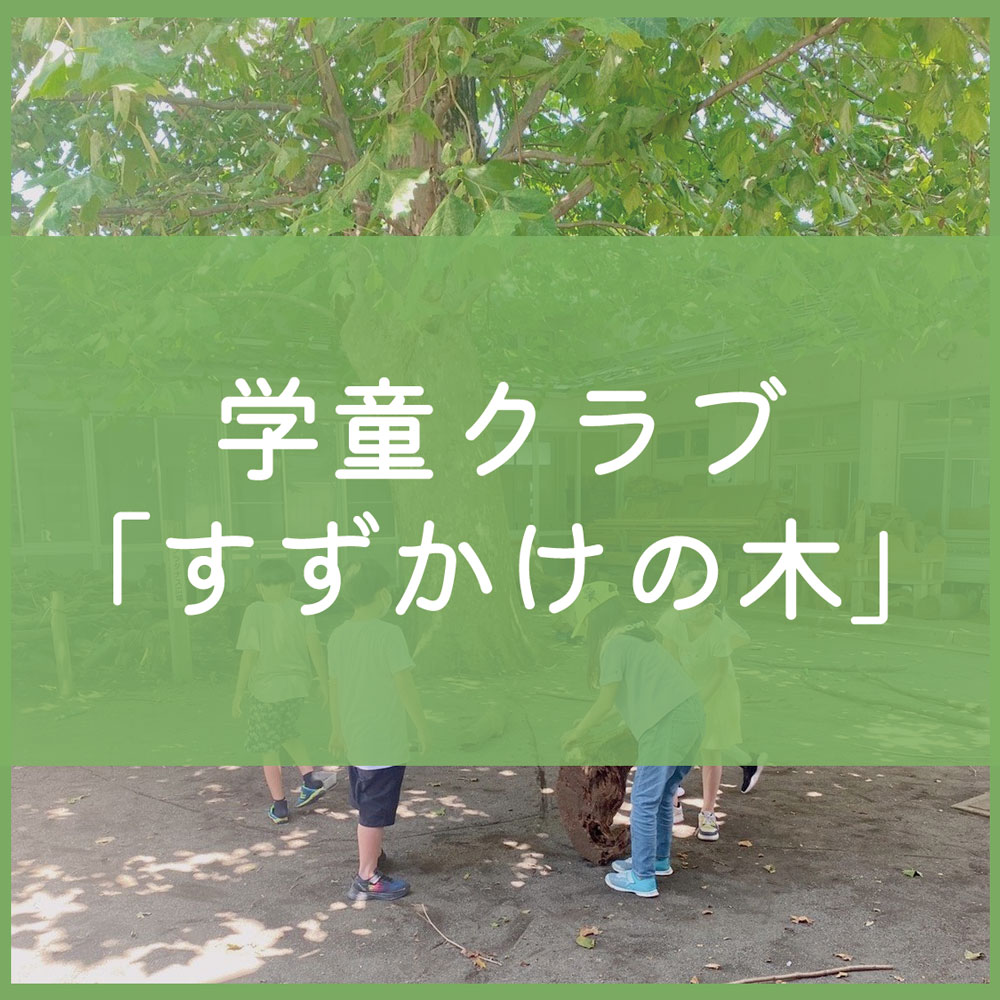小学校
先生コラム
二学期のはじまりに
大忙しの二学期
二学期が始まり、2週間が経ちました。
始まってすぐに主に公立校の登校見守りをしている近隣の方から連絡を受けました。小学生の登校経路からは少し外れるのですが、通称黒門と言われるところで見守りをしていると、明星の子どもたち(主に高校生でしょうか?)は気持ちよく挨拶をしてくれるそうです。先学期の終業式や今学期の始業式でも話しましたが、人とのコミュニケーションにおいて挨拶が重要だと思いますので、続けてくれたらと思っています。
二学期は行事も多く、こどもたちも大忙し。まずはその第一弾として夏休み作品展が行われました。始業式の登校の様子を見ているとどの子も通学カバンには入らない大きな荷物を抱えています。隙間から見えているのはおそらく作品展に出品する作品。夏休み期間にがんばって作ったのでしょう。時には家族にヒントをもらいつつ、難しいところは手伝ってもらいながらも完成させたと思うのです。賛否あるかとは思いますが、わたしはそうやって家族が協力することも大切かなと思っています。
年々そうなってきていると思うのですが、何かを調べてまとめる子が多くなってきたと思います。今年も不思議に思ったことや興味を持ったことについて、調べてまとめている子が多くいました。しかもなかなかの大作が多く、画用紙数枚にわたって調べたことをまとめ上げている作品もありました。内容も多岐にわたっています。生物の多様性について興味を持った子、普段はあまり気にもしなかったことに着目した子、そして一つのことを継続的に観察した子。中にはとても時間がかかる作業をした子もいました。完成度もそうですが、自分なりに作品展のテーマを決める、その感性が素晴らしいと思いました。
印象に残った作品はたくさんあります。そんな中、富士山に登って下山した後、周囲の施設に捨てられたゴミの多さに目がいったことをまとめた作品がありましたが、その感覚は正しく、その気持ちを忘れないでほしいと思います。
そしていよいよ運動会の練習も始まります。近年は9月に入ってもなかなか涼しくならず、熱中症指数をチェックしながらの練習になりますが、6年生や9年生はそれぞれの最高学年として、全体を引っ張っていく役を担います。この経験こそが明星学園が大切にしている柱の一つでもあります。うまく行ったことも、苦労したことも、それら全てをこれから先の生活に役立ててほしいですね。人に言われて動くのではなく、自らやるべきことを見つけ、動く。自主自立の精神を大切にしてがんばってほしいと思っています。今年の実行委員長は6年1組の隄さくらさんです。ここでは実行委員全てを紹介できませんが、その実行委員と力を合わせて、明星学園らしい運動会にしていきましょう。
そして10月に入ると台湾からの留学生が明星にやってきます。お互いに母国語が英語ではない留学生と交流し、英語やボディランゲージ、時には漢字も使ってコミュニケーションをとって、留学生たちが「日本に来て良かった」と思ってくれる期間にしたいですね。その時、わたしたちは日本の何を伝えれば日本をより豊かに理解してもらえるのかが課題になると思いますが、これはまたなかなか難しいところです。
これから6年生にとっては、いろいろな行事の中心となる機会が多いので、体調を整えがんばってほしいと思っています。
季節の移り変わり
今年はなかなか梅雨明けしない東京地方と思っていましたが、6月には開けていたそうですね。四季の移り変わりを楽しむことができることも日本の良さであると思うのですが、近年はなかなかそうもいかないようです。今年は「秋」を楽しむことができるでしょうか。例年だと運動会の頃に山から平地に降りてきた赤トンボ(アキアカネ)が目立つようになりますし、前後してキンモクセイも開花が始まると思います。朝晩、涼しくなった青空の下で子どもたちが元気に走り回れるよう願っています。
生き物の世界も変化があるようで、温暖化によって今までよりもさらに北の地域で発見されることもあるようです。逆に北海道にしかいない生き物が、北海道内で見られなくなることも、この先あるのかもしれません。
またこの夏も「クマ」のニュースがたくさん届きました。しかしそれはほほえましいニュースではなく人の生活に関わる厳しいニュースです。山に食べるものがなくなり、市街地にまで降りてきて、時には家の中にまで入ってくるクマ。人間の手では太刀打ちできない相手だそうです。大切に育てた作物を食べられたりということもあるでしょうし、学校の近くに出没したということで、登下校に不安を抱える地域もあったりするそうです。東京ではなかなかないことだとは思いますが、都内の小学校でも西の方の学校では学校内にクマが入ってきた例はあります。これから先、全ての生き物が共存するにはどうしたらいいのか、重要なテーマとなるでしょうね。生き物好きな明星っ子に、ぜひそのあたりを考えてほしいと思います。
ほんのちょっとの紹介
夏休み、読書は進みましたでしょうか?と聞いているわたしはなかなか進みませんでした。読みたい本は溜まる一方、読書の時間の優先順位がどんどん下がってしまっています。読書の秋に向けて立て直さないとと考えていますが、うまくいくかどうか…。
吉祥寺に出た時は大きな書店に寄って、どんな様子か探っているのですが、特に夏休み中は「課題図書」と呼ばれる本が平積みされていました。新作が多く、古くから読まれてきた本はまずありません。そこが残念ですね。
夏休み中、「トーベとムーミン展」や「レオ・レオーニの絵本づくり展」といった本や絵本に関連する展覧会がありましたし、エリック・カールのプレイパークに行った子もいるかもしれません。時間に余裕のある夏休みだからこそ、そういった機会に触れ、自分の世界を広げてくれるといいなと思っています。
さて、本の話題に戻りますが、これからスポーツの秋、食欲の秋、読書の秋といったとてもいい季節になるので、それらに合わせていろいろと読んでほしいと思います。
わたしからは食欲の秋と遠足シーズンに合わせた本を…。秋といえばさつまいも!焼き芋の季節です。幼稚園での出来事が描かれている本ですが、少しお兄さんお姉さんになった小学校低学年の子どもたちが、読み聞かせてもらうのではなく、上から目線?で自分で読む楽しさを知ってほしいと思っての紹介です。
『おおきなおおきなおいも』(市村久子 原案、赤羽末吉 作・絵、福音館書店)
そしてもう一冊は保護者向けにはなってしまうものですが、ひとまず…。本の内容というより、悩みを抱えている人が世の中にはたくさんいるのだという現実をまずは認識しないとならないと思い、紹介します。と同時に猫好きなわたしにとっても読みやすい本でした。『猫を処方いたします。』(石田 祥 作、PHP文芸文庫)
※画像はものつくり同好会で作った万華鏡です。
(校長 照井)