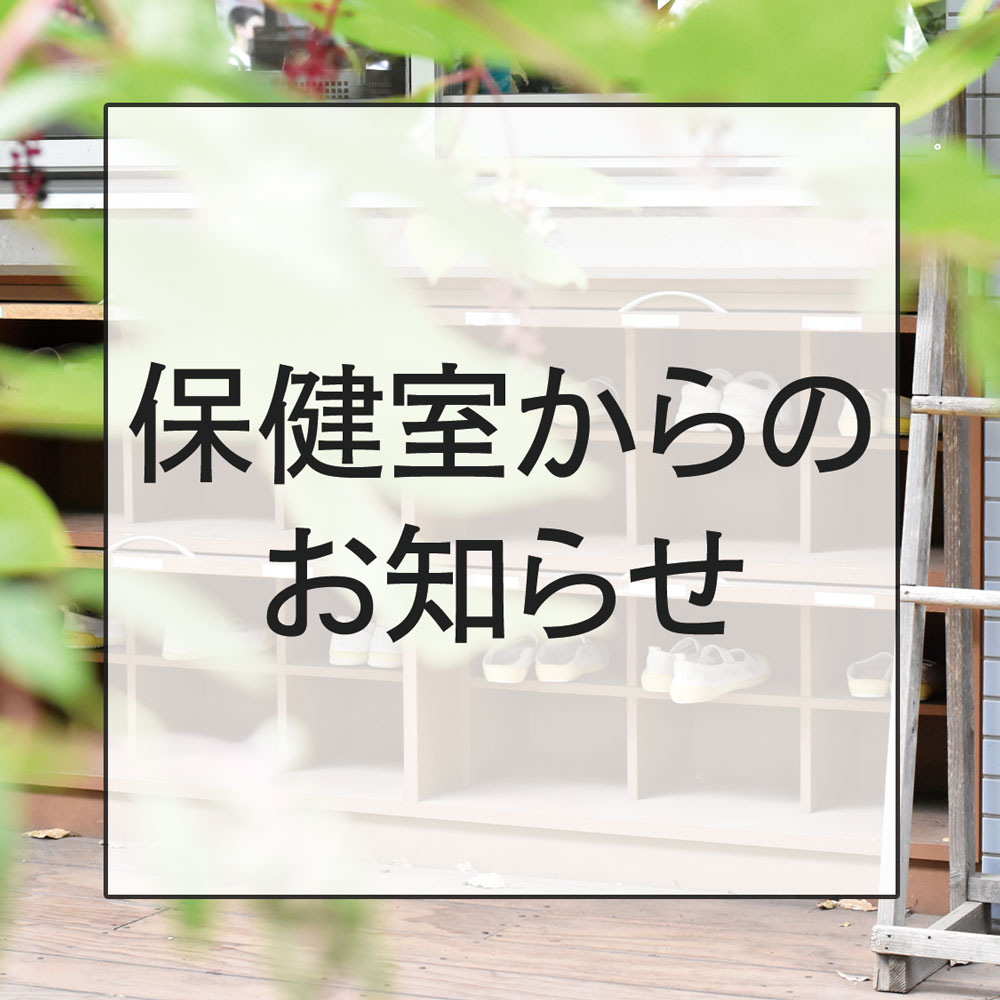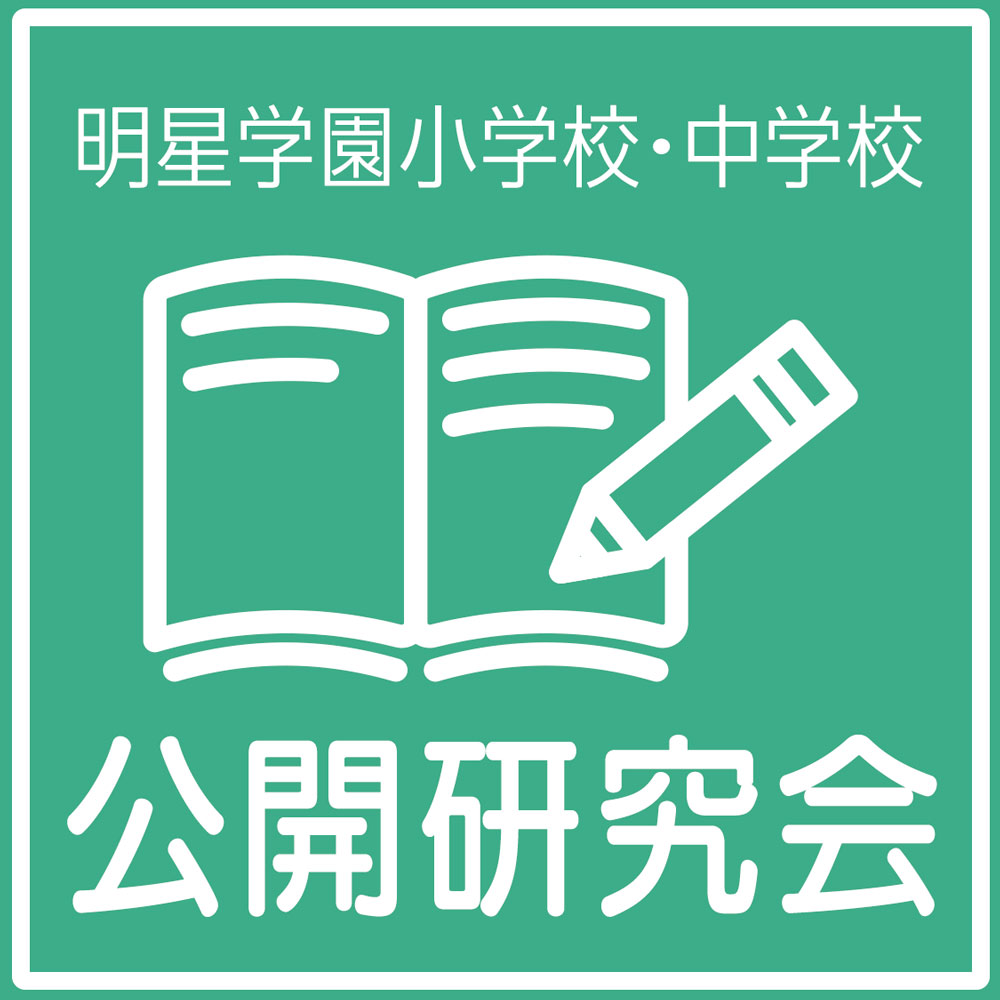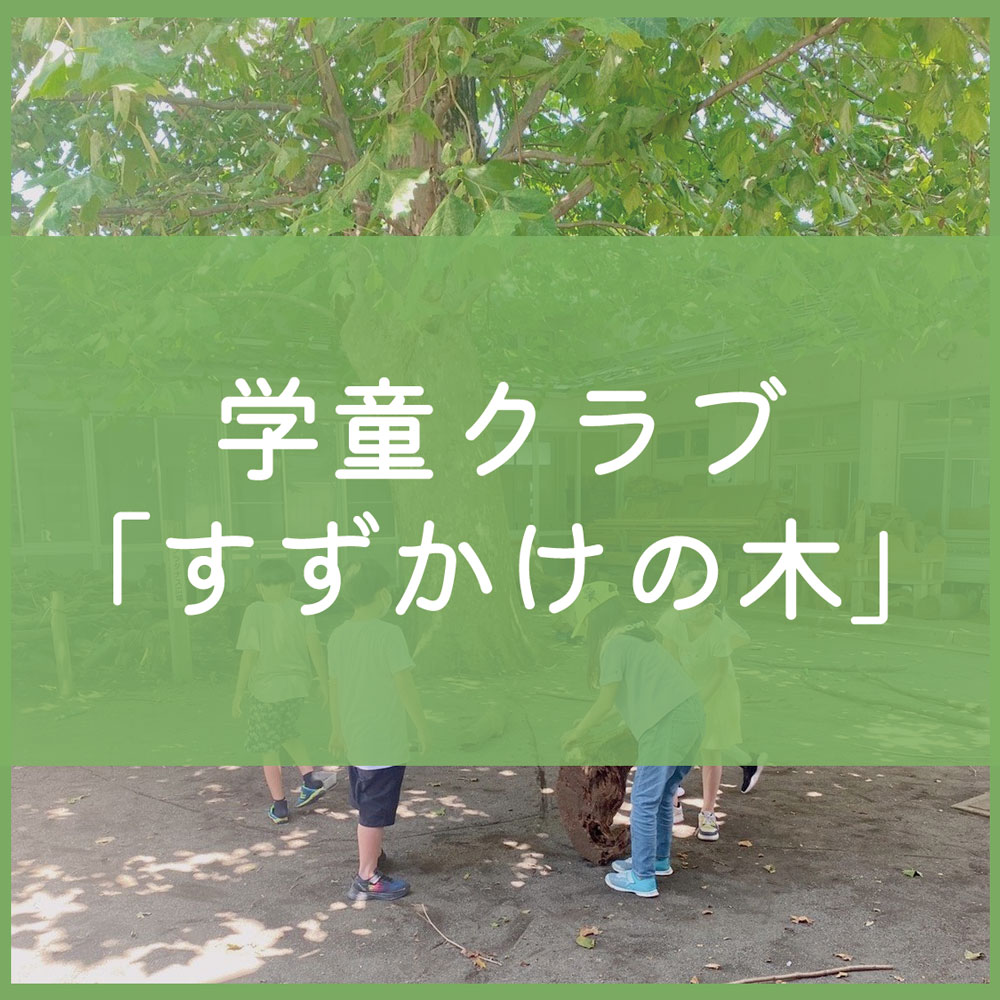小学校
先生コラム
二学期も残りが少なくなりました!
あっという間
つい先日、運動会が終わったと思ったら、もうすでに11月が終わろうとしています。月日の経つのは本当に早いものです。二学期は大きなイベントも多く、運動会後は6年生が奈良に修学旅行に出かけました。新しい総理大臣の発言で鹿がクローズアップされている2泊3日の奈良旅行です。今年もいくつかのハプニングはあったようですが、無事に東京へと戻ってきました。6年生はとても楽しかったようで、翌週は満足げな顔を見せてくれました。台湾からの留学生受け入れ、運動会、修学旅行、バザーと大きなイベントが続き、体力的にもなかなか厳しい期間ではありましたが、そこはさすがに6年生。がんばって乗り切ってくれました。
またその修学旅行後に行われたバザーはあいにくの雨天ではありましたが、バザー委員さんをはじめ、保護者の方々と在校生・卒業生、そして地域の方々の楽しい集いの場となりました。本校の受験を前に見学しにきたご家族もいらっしゃいましたが、保護者の方々のエネルギーに感心し、自分たちが入学し保護者になったら、ぜひあの輪の中に入りたいとおっしゃっていました。保護者の方々も、次の日は平日なのでお仕事等あったのだと思いますが、夜遅くまで片付けなどにあたっていました。今年度も楽しいバザーをありがとうございました。私は1階の図書室で入学広報の仕事をしていて、お昼頃になったら目の前で作っている焼きそばを買いに行こうと思っていたのですが、広報が落ち着いたタイミングで外を覗くと、焼きそばには長蛇の列。そして少し列が少なくなってきたタイミングで「売り切れました〜」との声。今年は焼きそばを食べることができず残念でした。
二学期も残り少なくなった11月22日に毎年行っている小中学校の公開研究会が行われました。今年も外部から100人を超える参会者が来校され、小中学校の授業を観ていただきました。ただ今年はインフルエンザなどの流行する時期が例年より早く、公開研究会の前の週ぐらいから小中学校で学級閉鎖や学年閉鎖が相次ぎました。公開研究会の前々日まで閉鎖だったクラスや、残念ながら当日も閉鎖のままというクラスもありました。また閉鎖ではないクラスも、人数が少なく体育のゲームが行えないなどの事情もあり、クラスの変更といった工夫もしながら当日を迎えました。毎年のことではありますが、教科書を使わない明星学園のカリキュラムは、独りよがりの実践にならないよう、客観的なご意見をいただき、精査していかなければなりません。我々にとっては日頃の実践を世に問う大事な研究会です。人数が少なかったり、閉鎖によって久しぶりの授業であったりと提案者としてはいろいろとやりづらさがあったと思いますが、それでも忌憚のないご意見をいただけた、いい研究会となりました。ここででたご意見等を真摯に受け止め、今後の我々の実践に活かしていきたいと思います。
それにしてもこの感染症の流行する時期が、明らかにイレギュラーな気がします。先日、本校の学校医の先生と話す機会があったのですが、その先生も今年は随分と早まっているとおっしゃっていました。原因は何かということは一言では言えないのかもしれませんが、マスクの着用率もあるのではとのことでした。確かに12月ぐらいになるとインフルエンザの予防などから、電車の中などでもマスク姿が増える気がします。学校内でもそのような傾向はあるのではないでしょうか。だとするとインフルエンザのウイルスは、人間が油断している隙にその勢力を増やそうと企んでいるのかもしれませんね。
季節の移り変わり
みなさんは今年、秋を感じましたでしょうか。いつまでも夏の暑さが続き、ところがいきなり冬の寒さがやってきた感じで、過ごしやすい「秋」を楽しむことができなかった気がします。そして各地の紅葉の便りに気がつく暇もなく初雪のニュースも届いています。先日水戸で観測された初雪は平年より29日も早かったそうですね。今までの常識が常識ではなくなっている気がします。
日本は四季がはっきりしている温暖でとてもいい気候の国だと思っていましたが、いつまでもそう言っていられないかもしれません。地球温暖化によって、このまま日本は亜熱帯化していってしまうのでしょうか。そのことが影響しているのかわかりませんが、東北各地で問題になっているツキノワグマが、冬眠しないかもしれないという話まで出てきました。冬眠しないとなれば、その間の栄養源となる食料が必要です。しかし冬季の山には十分な食料はありません。となれば食料のある場所を探して歩くことは当然の行動となります。ツキノワグマは里に降り人間の食べ物やゴミをあさったりします。それでも十分に食料を確保できなかったら…。
全てが温暖化のせいではないと思いますが、明らかに動物の環境には変化が現れています。温暖化によってホッキョクグマの生息地が減少しているという話はもちろんのこと、これからは国内のツキノワグマの動向にも注目していきたいと思っています。
ほんのちょっとの紹介
先月の学校だよりで、「いよいよ読書の秋でしょうか。」と言ったにもかかわらず、「2.」で書いた通り秋を感じる期間が長くなく、読書の秋を楽しんだ感じがなかった10月から11月にかけてでした。
さて、「季節の移り変わり」のところでも書きましたが動物界にもいろいろな変化が起きています。しかし少し前までは動物は動物らしく生きていた時代もあり、そんな動物の生態を織り込みながら描かれている本を今回は紹介します。
まず日本の作家さんで動物を生き生きと描いているのはなんと言っても椋鳩十さんだと思います。『片耳の大シカ』や『山の太郎グマ』などといった名作がたくさんあり、いろいろな形で出版されています。その中でも『大造じいさんとガン』は教科書に載っていたり、明星でも昔から5年生の教材として扱ってきたりした作品です。『大造じいさんとガン』は教材として使うことがあるかもしれないので、まずは他の作品を読んでもらえればと思っています。私は小学校の時、この椋鳩十さんの作品が大好きでした。
もう一つの紹介は海外の作家さんです。こちらはミサゴという保護鳥を中心にしたお話で、お話の展開も現代的な部分やテーマ性もあり、とても読みやすい作品です。そしてなんと言っても情景描写が素晴らしく、登場人物の行動もまた美しいのです。同じ作家さんから動物を題材にした作品が何冊も出版されているので、他の作品も読んでもらいたいですね。『ミサゴのくる谷』(ジル・ルイス作、さくまゆみこ訳、評論社)
(校長 照井)