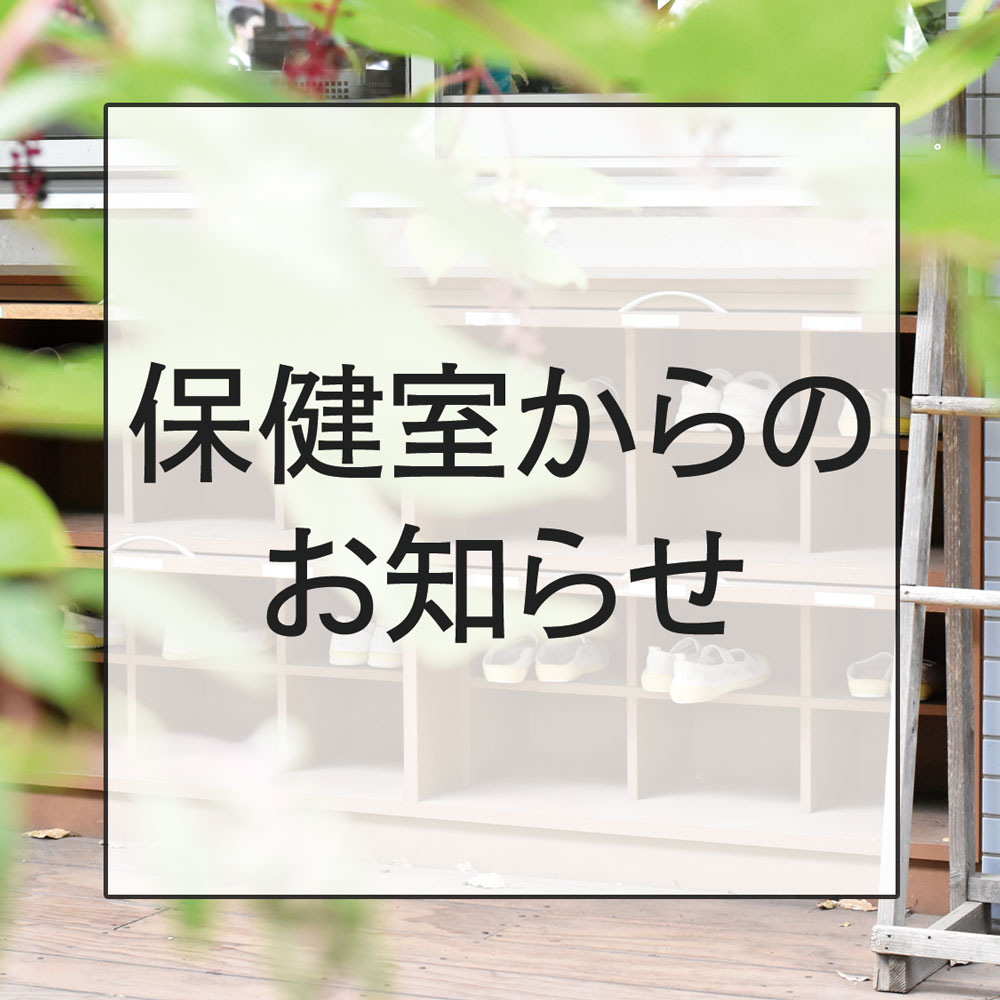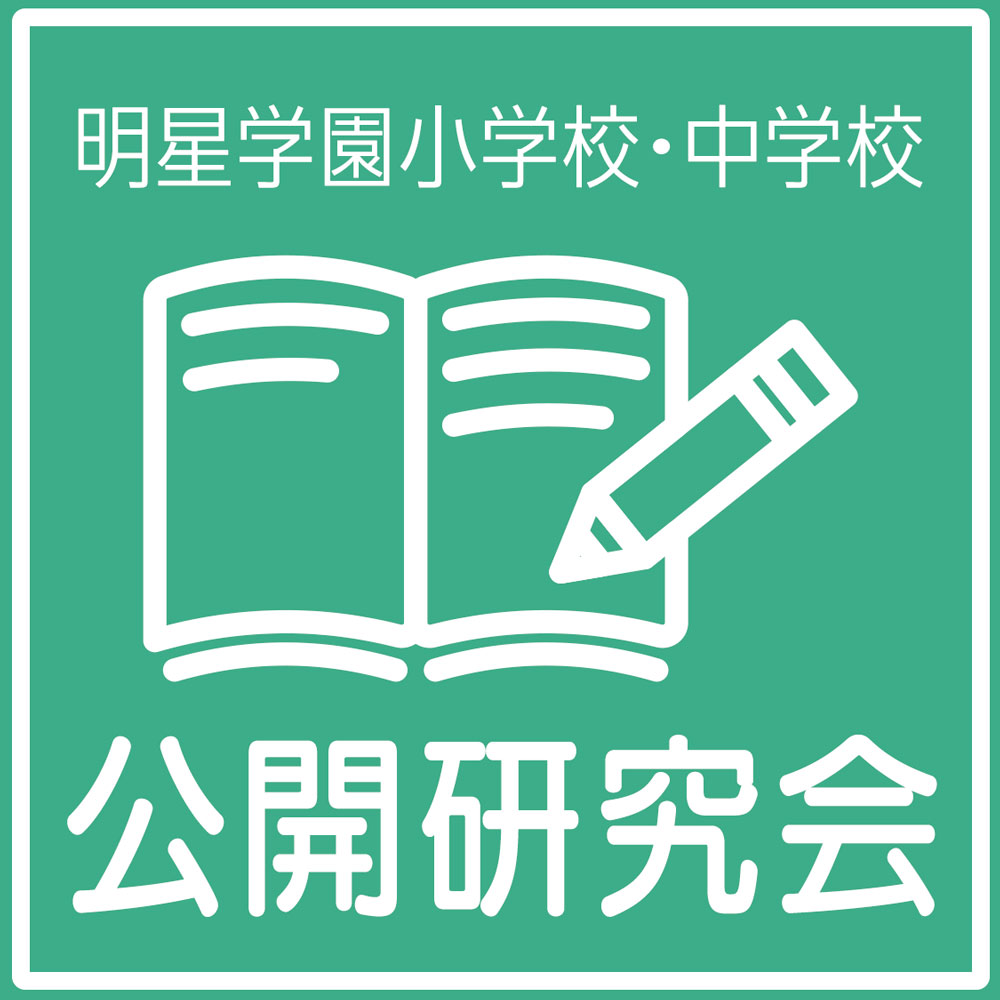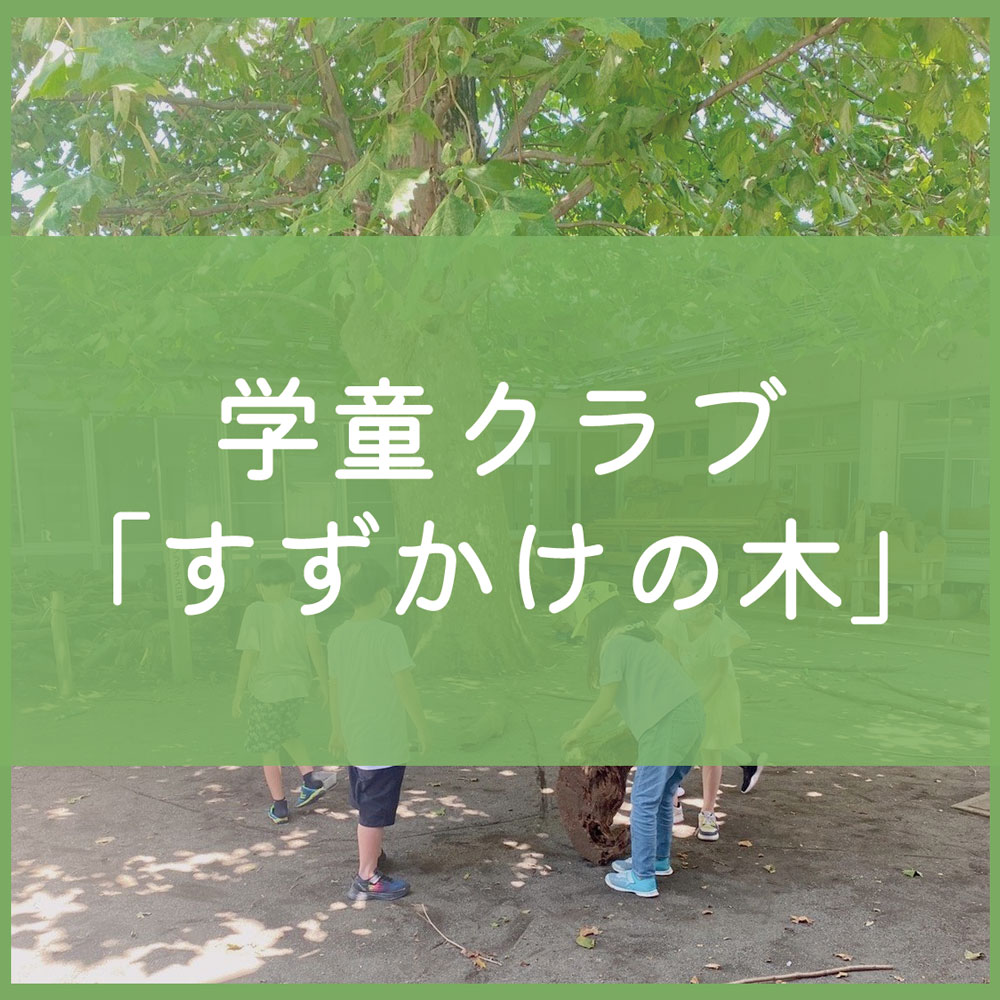小学校
先生コラム
創立記念日に寄せて
101年目のスタートにあたり
昨年度の創立100周年が終わり、いよいよ101年目のスタートです。しかし101年目に入って学校が変わるかと言えば、それほど大きな変化はありません。もちろん不十分なところは改善していくべきですし、新しい教材や指導法の開発などにも力を注がなければならないと思います。ただ、大きく変化しないのはやはり建学の理念というものが確立しているからではないでしょうか。「個性尊重」「自主自立」「自由平等」の三つは揺るぎないものだと思います。たとえば大正時代、一つのクラスに70人も80人も詰め込まれていた時代に、「個性尊重」などできるはずもありません。そんな時代に「個性尊重」を謳い30人前後の少人数クラスを作り、一人一人の子どもをていねいに見ていこうとした先人たちの想いは、経営とのバランスを考えれば相当な覚悟がいったことだと思います。ではそれが新たな100年を迎え、少人数制をやめるかと言えばそんなことはありません。「自主自立」「自由平等」についても同じことが言えます。年齢的に多くの卒業生を見てきましたが、どの卒業生も自分自身の足で立ち、自分の信じるものに向かって自由に生きているのだと思います。そのような建学の理念があるからこそ、方針の大きなシフトなどあり得ないのです。
ただし変わらないからといえ、そのままでいいかと言えばそうではありません。「個性尊重」「自主自立」「自由平等」の大もとは変わらないとしても、時代による工夫は必要です。100年前と現在では社会の状況は全くと言っていいほど違います。100年前の「個性尊重」と2025年の「個性尊重」は同じにはならないのです。では2025年は「個性尊重」「自主自立」「自由平等」にどんな味付けをするのか。新たな100年のスタートとなる今年はそこが問われているのだと思います。
大きな変化ではありませんが、今年度から子どもたちの困り事にさらに寄り添うことができるように、学校側の体制を整えました。そして専任教員の数も増やしています。新しい先生をお迎えし、これからどんな教育が行われ、どんな学校生活が繰り広げられるのか、とても楽しみであります。ただしそれらの変化が子どもたちの成長や、保護者の方々の信頼を無視した変化であってはいけないと思っています。
私立学校はそれぞれ建学の理念を持っており、その理念を元に教育活動を行っています。その理念に共感していただき、入学を決めていただいた部分が大きいと思います。ゴールデンウィークの初日に新宿のNSビルで私立小学校展が行われ、私も「なんでも相談コーナー」を担当しました。多くの私立小学校が一堂に会し、有名校のブースは行列ができるほど賑わっていました。「なんでも相談コーナー」は個別の学校の相談ではないので、内容は多岐にわたるのですが、そこに来る方は私立学校に何を求めるのかまだはっきりしていない方が多いように感じました。「私立小学校ってどんなところ?」「公立小学校と何が違うの?」そんな質問も多いのです。もちろんよくわかっている方は直接お目当ての学校のブースに行くので、「なんでも相談コーナー」に来る方はその前の段階という感じにはなると思います。明星学園の魅力を伝えていくことも大事ですが、私立小学校ならではの教育の魅力を伝えていく必要もあると感じました。と同時に、明星学園の魅力を多くの方に知っていただくためにも、目の前の子どもたちが「いつも元気でニコニコ」していられる学校にしていくことが大事だと思っています。
創立101年目、学校は建学の理念に少しずつ時代の味付けをしながら歩み続けます。
ほんのちょっとの紹介
今回はいつもとはちがった本の楽しみ方を紹介します。『おおきなかぶ』という本は、誰しも一度は読んだことがあるというぐらい、よく知られている本だと思います。その多くは福音館書店から出版され、内田莉莎子さん訳・佐藤忠良さん画の絵本だと思います。しかしこの『おおきなかぶ』の本は様々な形で出版されています。
たとえば田島征三さんもその独特な画風で『おおきなかぶ』を描いています。(田島征三作・絵、三起商行【ミキハウス】)また女優の中井貴恵さんが訳した『おおきなかぶ』もあります。(トルストイ作、ニーアム・シャーキー絵、中井貴恵訳、ブロンズ新社)先日、吉祥寺図書館に行ってみると、『おおきなおおきなおおきなかぶ』という本もあり、これもまた福音館から出ているものとは違います。(アレクセイ・トルストイ文、ヘレン・オクセンバリー絵、こぐま社編集部訳、こぐま社)
ストーリーの大筋は同じですが、登場人物がちがっていたり、カブの色が白色なのか黄色なのかというちがいがあったりもします。(本国ロシアではカブは黄色で表されるようです。)そして一番のちがいはカブを抜く時のかけ声。ここに訳者のちがいが色こくでます。
同じ話でこれだけ様々な形があるのは、それだけお話に魅力があるということでしょうね。読み比べてみるのも面白いかも知れません。
(校長 照井)