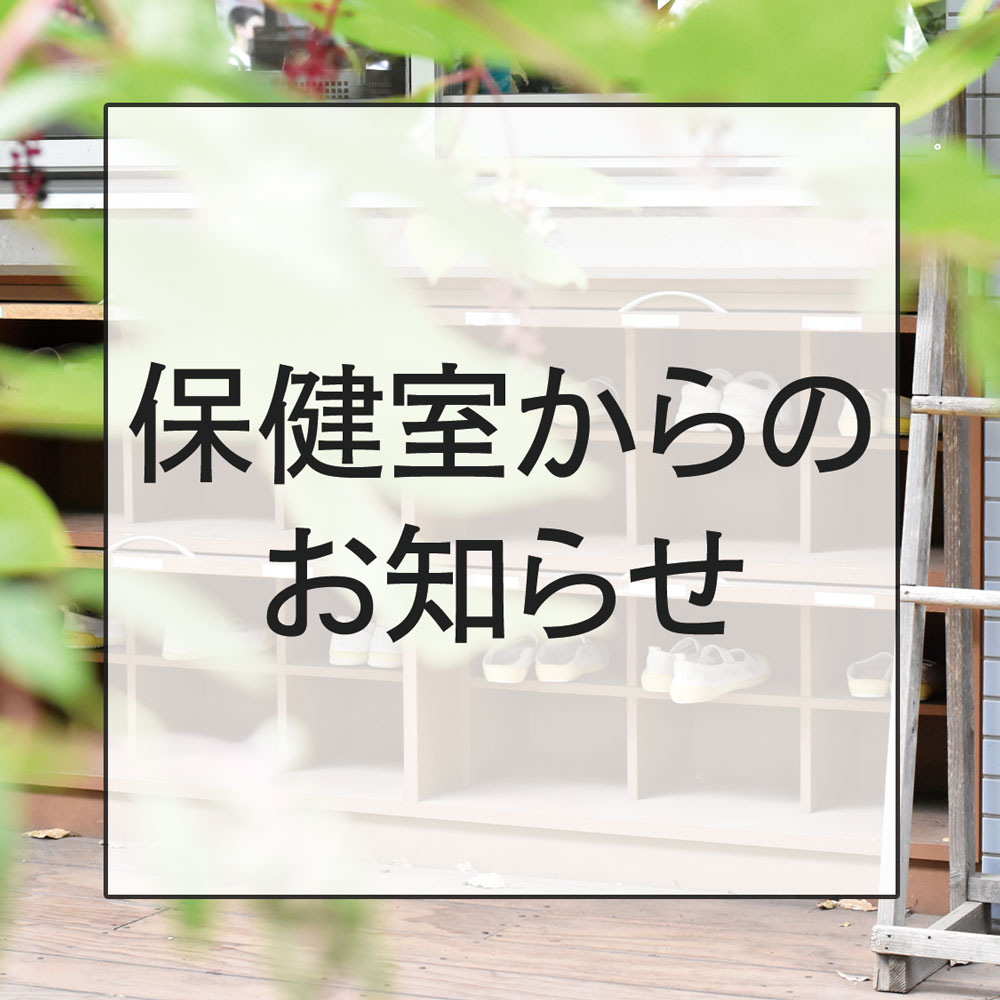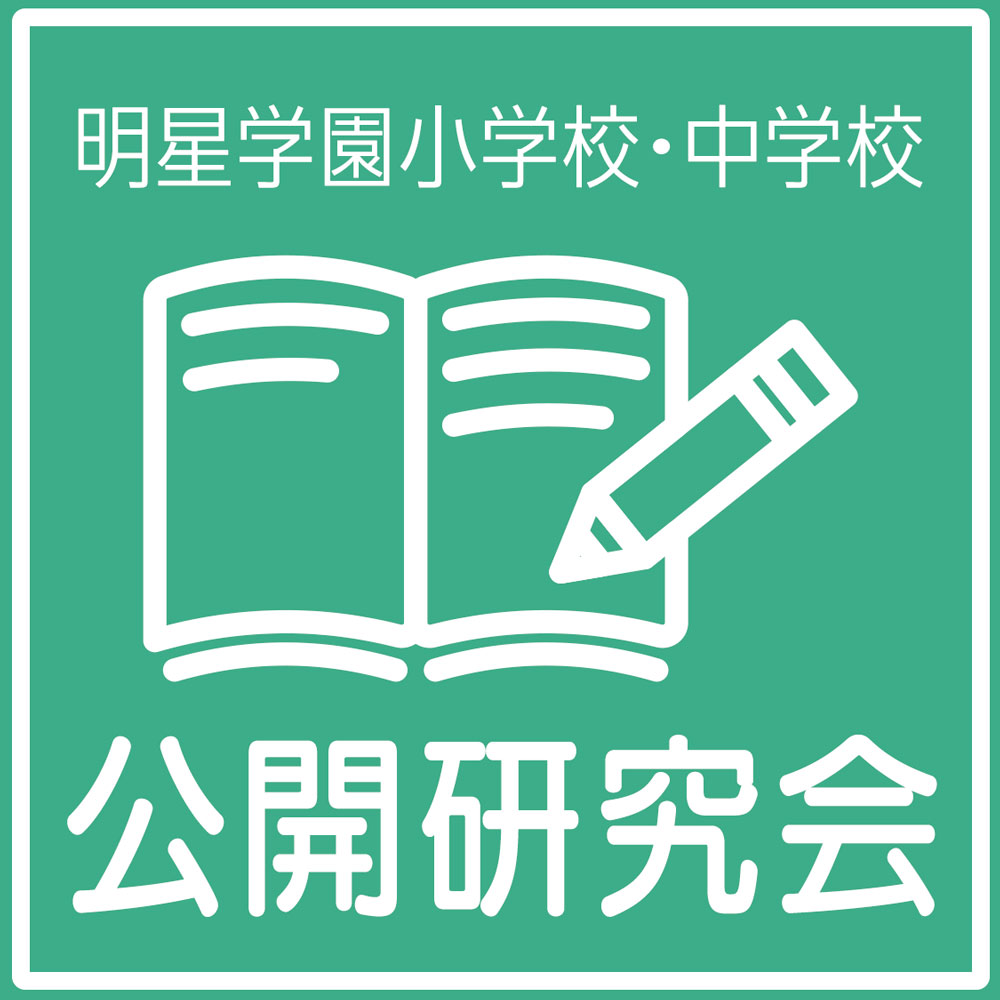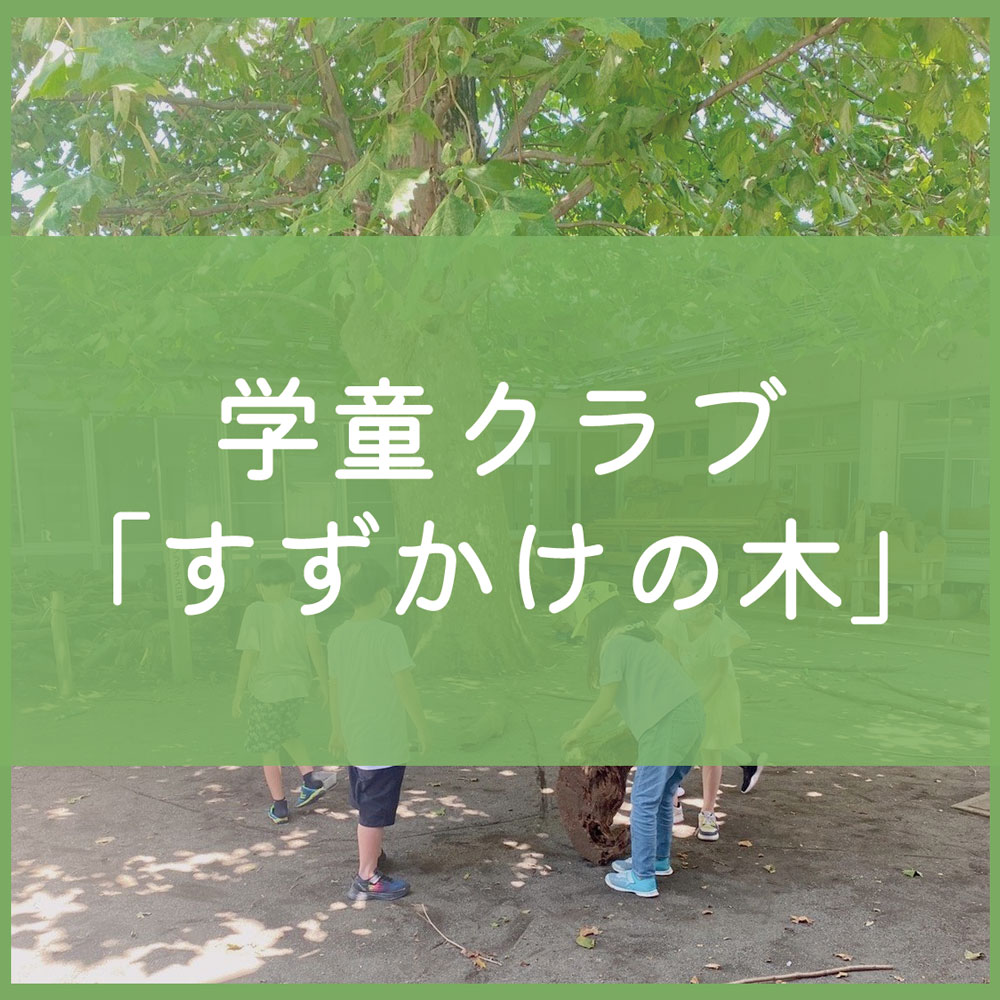小学校
北京モンテッソーリ国際学校から5名の先生が来校!!
11月20日、北京モンテッソーリ国際学校の理事長・幼稚園園長・小学校教員をはじめ5名の先生方が明星学園小・中学校キャンパスを訪問されました。
モンテッソーリ教育とは、子どもの「自ら育つ力」を尊重する教育法で、探究・自己発見・実践的な学習体験の重視といったキーワードで語られます。120年の歴史を持ち、現在世界140か国以上に普及しているようです。
児童中心主義として個性尊重・自由平等・自主自立の理念を持つ明星教育とは親和性を多分に持つ教育法です。

今回は1年生の「体育」「総合」の授業にご案内、また中学校「木工」「工芸」の授業の説明を教科担当の先生にしてもらいました。
私も伊野副校長と共に同行し、先生方の質問に答える中で、あらためて明星教育の独自性と具体的な工夫を認識する貴重な機会となりました。
◇1年体育(冨田教諭)の授業~「走る」
グラウンドにひかれた曲線の両端に分かれた子どもたち。双方から一人ずつ走り始め、出会ったところでハイタッチ、そしてジャンケン。負けた子は「負けたー!」と大きな声で合図を送り、次の子どもが走り出します。何回かのジャンケンをくぐりぬけて・・・といった授業なのです。
ルールがしっかりしているので、子どもたちは混乱することがありません。ルールがあることで主体的に行動できています。これは子どもを支配するためのルールとは全く異なります。それでいて、楽しく、結果的にかなりの距離を走ることになります。
また、「負けたー!」の声があちこちで飛び交っているのも印象的でした。子どもたちにとって、負けたくないというこだわりは友だち関係にぎこちなさを生じさせる原因ともなります。負けるのが怖くて挑戦することから逃げる子どもも出てきがちです。勝つこともあれば負けることもある。負けたら「負けたー!」とあっけらかんと叫んで列の後ろに並び、再チャレンジする。何か、大切なコミュニケーションの練習をしているようで、モンテッソーリ国際学校の先生方も共感してくれました。
◇1年総合(北村教諭)の授業~「クリスマスリースづくり」
教室をのぞくと、黒板の前の先生を囲んで子どもたちは真剣にリースづくりの説明を聞いています。土台となるつるは、子どもたちが教室の前の花壇で育てたアサガオのもの。いい具合に枯れていて、まさにこの時期の単元なのだと思いました。
先生の説明が終わると、質問のある子が手を挙げます。1年生でこんなことができるのだと新鮮で、正直感動しました。作業開始の合図で子どもたちはグループに分かれ、それぞれが飾りを作り始めます。そのための材料は用意されていますが、それをどのように使うかは子どもに任されます。それがつるにデコレーションされていくうちに立派なクリスマスリースが完成していました。
モンテッソーリ国際学校の先生方も、このグループで協力して一つのものをつくることには大変感心されていたようです。何より「ものづくり」をする子どもたちの表情が素敵でした。
ちなみに、次の「総合」の授業は何をするのか先生に聞いてみたところ、クラス花壇に枯れたまま残っている「オナモミ」の実の観察だそうです。とげとげの実で、「ひっつき虫」と言われ、子どもの頃よく遊んだ、あの小さなラグビーボール型の実です。
「総合」の授業の題材が、こんな身近にあるものだというのが素晴らしいと感じました。言われなければ気づかないようなそんな小さな存在、でもそこに探究の種がたくさん転がっているのですね。すでにその植物の名前が私の頭から消えていましたが、近くの男の子に尋ねたところ、「オナモミ!」、大きな声で答えてくれました。たいしたものです。
◇「木工」(山元教諭)、「工芸」(河野教諭)の授業について
生徒作品がたくさん置かれた、木工室と工芸室。作品だけでなく、素材や道具が用意され、他の学校では感じることのできない明星教育を象徴するような場所でもあります。自由や個性といった理念は、芸術教育の位置づけで具現化しているのを感じます。
モンテッソーリ学校でも芸術に関する関心は高いらしく、具体的な質問をたくさんされていました。工芸室でモンテッソーリ国際学校の小学校校長先生が見せてくれた当該校での織り機を使った授業の写真。明星そっくりで全員びっくりした瞬間でもありました。
- 工芸室での風景
- 木工室での風景
- 学園資料室を訪問
その後、渡辺京理事長を交え、両国における教育環境、保護者と学校との関係、さまざまな質疑応答がありました。特に、このような自由教育の実践を明星学園が100年以上にわたり続けてこられた秘訣は何なのかという質問が印象的でした。北京モンテッソーリ国際学校は創立から20年、海外子女のために設立されたということですが、理想の教育をいかに続けられるかを学ぶために視察されているようでした。
我々にとっても、視野を広げる良い機会となりました。また、明星教育を外に向かって語ることは、自分自身を、また自分たちの実践と向き合う機会ともなります。今後も、日本の内外を問わず、教育について語り合うことを大切にしていきたいと思います。
(学園広報 堀内)